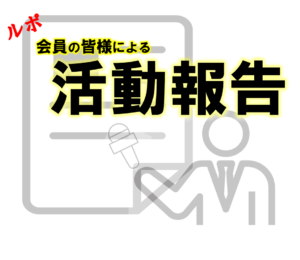私の提言 「成長する場」を設計する
東洋大学 野中 誠

私は長年にわたり、大学においてPBL(Project-BasedLearning)型教育を実践している。学生たちは実務を模した課題にチームで取り組み、得られた情報をもとに問題を発見・定義し、方法論を駆使して提案をまとめる。最後には「プレゼンテーションバトル」の場を設け、全員が真剣に議論する。
この経験を振り返ってみると、知識やスキルの伝達ももちろん必要だが、「学生が成長する場」をいかに設計するかが大切であると感じている。最初は小さな成功体験を積み重ねて自己効力感が得られることを重視するが、次第に課題のハードルを上げていき、これをチームの力で乗り越えていく。プレゼンバトルを設けることで学生の内発的動機づけを促し、細かな工夫を随所に散りばめながら「成長する場」を継続的に改善している。学生同士が互いに刺激を受け合い、視野を広げていく姿を目にするのは教員として大きな喜びである。
「成長する場」の設計は、大学教育だけでなく企業活動にも通じる。品質管理や改善の取り組みも、目の前の課題を解決するというプロセスを通じて、参加する人々全員が成長できる場としてデザインすることが、組織全体の質の向上につながると考えている。改善活動はややもすると形骸化しがちな側面もあるが、参加者の成長を後押しする仕掛けとして位置づけたい。組織としての成果と、組織および管理者を含めた個々人の成長のベクトルを揃えることは容易ではないが、参加者の内発的動機づけに働きかける取り組みを心がけたい。
近年は生成AIのような新しい技術が次々と登場し、知識や解法に簡単にアクセスできるようになった。その使い方次第で、参加者の成長を促すツールにも、逆に阻害するツールにもなり得る。こうした技術と向き合いながら、「成長する場」をどう進化させるかが問われている。
学会は、「成長する場」を学会コミュニティおよび社会に提供する器である。世代や立場を超えて人々が集い、互いに学び合い、新しい価値を見出す。学会として、このような場のデザインと継続的な改善を実践していくことが、社会から期待されていることだろう。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2026年2月17日2026年度 通信教育 品質管理基礎講座
お知らせ2026年2月17日2026年度 通信教育 品質管理基礎講座 お知らせ2026年2月16日ニューズNo,426を読む
お知らせ2026年2月16日ニューズNo,426を読む お知らせ2026年2月16日トピックス
お知らせ2026年2月16日トピックス
日本最大級の品質経営総合大会「クオリティフォーラム2025」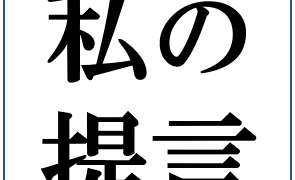 お知らせ2026年2月16日私の提言「AI時代の品質議論:伝統と革新の架け橋として」
お知らせ2026年2月16日私の提言「AI時代の品質議論:伝統と革新の架け橋として」